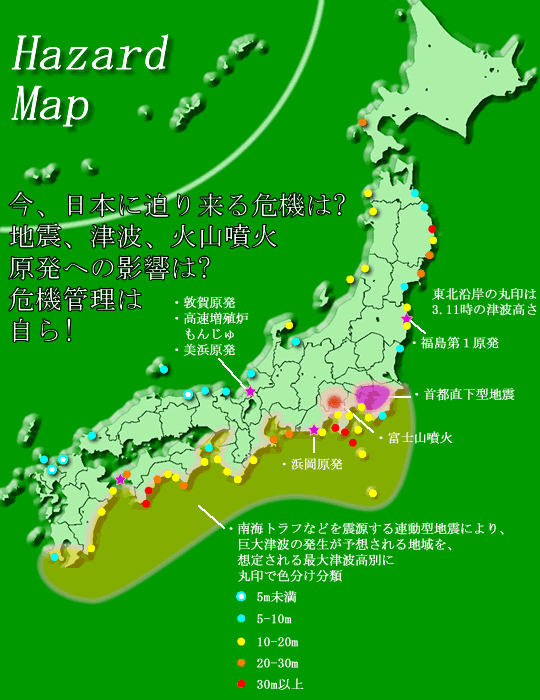
波高別色分けは「南海トラフ地震の被害想定by有識者会議」と「日本海における大規模地震での津波想定by有識者検討会」共に朝日新聞デジタル掲載を参考にしました
Clickしてお住まいの地区の情報も検索できます
また3.11の東北沿岸各都市の被災状況はこちらのGoogleMapにてご覧ください
何が最良の危機管理か? What,When,Where,scaleなどの情報を早期に得ることはもちろんですが、もう一つのWhereとhowも大切! それは安全な避難場所に早く辿り着くこと!
日頃実施されている避難訓練の精度を高め、習慣化する上で有効と思われる手段について、このページでは幅広く提案していきたいと思います
誰もが積極的、且つ定期的に参加するには? 最初に提案したいのが避難場所をパーティー会場化する案です
そこでは賞味期限の迫った備蓄食料や飲料を参加住民に振舞い、またご当地アイドルを招待してのイベント開催も、AKB48が行っている被災地慰問のミニコンサート同様に集客(参加者の増加)効果あり! と思います
掲載中のご当地アイドル・G-POP・ページを参照しながら、津波避難訓練を実施中の市町村とご近所のご当地アイドルを結びつけるようなページ展開、確実に再発する地震や津波から身を守るための手段、そして原発問題も含めて、今後の日本を発展的に捉えられる情報やニュースメディアでは配信しずらい情報にもtwitter Time Line集のページにてスポットを当てます
ご期待ください。
youtube再生はこちら
・東日本大震災から3年経過しましたが、図示のような災害に関する対策が車両や部品のメーカーサイドでなされることはありませんでした。
それは100%の確実性と安全性を確保できないからです。 当然のことながら作動不良を起こせばリコールにつながります。
ですが南海トラフ地震で予想される津波は3分から20分で沿岸都市に到達します。この状況下で大切なことは100%の確実性が得られなくても、より生存確率を高め一人でも多くの人命を救う手段の実用化です。
・動画と下記する説明事項は徒歩圏内に十分な高さの避難場所がない、或いは身内に高齢者や子供などの避難弱者がいて車利用しか選択肢がない時、などに有効な提案内容になってます。
・図示してきた装置自体は既存の技術を組み合わせたもので、市販されている一般的な仕様の車種であれば、使用中の車両にプラスチックや金属製の締結ベルトまたは車体への穴あけとボルト・ナットによる締結などの工程で整備工場にて後着け可能と思います。
・町工場にて製造する場合、新規に取得する技術はハイパロンなどの型抜き、接合溶着技術程度で、後はボンベ(高圧ガス関連の法規も要チェック)のスプール・バルブへのワイヤー取り付けアタッチメントの試作などで実用化可能と思われます。
・普及させるには低価格がポイントになりますが、本提案で使用されるフローターの素材は車内に設置するタイプはPVCラミネート(一個当たり3-5万円程度)を、車体外側設置の場合はハイパロン(一個当たり5-10万円程度)とし、圧縮空気ボンベ(おおよそ10φ50cm、3L、100-150kg/cm²、膨張時300-450L)は背負うわけではないので鋼鉄製の低価格品(一個当たり3万程度)とし実用化後、量産すれば概ね車両価格の一割程度(軽車両を除く)にできるのではと考えました。
()内の価格は量産効果が出た上での当方の期待値であり試算結果ではありません。
・車体外側設置の場合はFRPなどの収納ボックス(上部にエァー抜き、下部に注水ダクトを設置)も必要になりますが、量産時にはSMCとアルミ型使用でフローター一個分程度のコストになることが期待できます。
・補助装備品として緊急脱出用ハンマーとLEDフラッシュライト、そしてアバランチトランシーバーが必要で、海上に流された場合を考慮し雪崩ビーコン(4万円前後)よりも格段に発信出力の大きな仕様のものとすべきです。
・重要、インフレータブルフローターとは使用時に空気を送り込んで膨張させて浮力を得るフローターの意味であり、エアーバックに使われている火薬などで作動するインフレーターのことではではありません。
・作動不良などを回避するにはインフレーターを用いるのではなく、圧搾空気ボンベのバルブを手動で開放するか、またはスプールに自転車のブレーキワイヤーなどを保持できるアタッチメントを取り付け、安全確認の上バルブを手動で車内から遠隔開弁すべきです。
・座席下部に設置するタイプはバルブ内径を小さくして膨張動作をスローに設定し(完全膨張まで一分程度に設定?)、走行中に子供のいたずらなどで開弁してしまったときは途中でバルブを閉めて膨張を停止できるなどの仕様にし、また車両の両サイドに膨らむ方式は通常走行時に作動しないような安全対策が必要です。
・設置場所は車両の重心位置(エンジンなどの重量物の配置)を考慮しなければなりませんし、また最低地上高に余裕があっても車体下に設置すると漂流時に転覆する恐れがあります。
・最後に、設計・製造に関わる技術的ノウハウは、既存のヘリコプター用エマージェンシーフローター、圧縮空気ボンベ、インフレータブルカヌーやラフトの製造メーカーにアドバイスを受けて取得し、地区の防災担当部署と地場の町工場の連携などにより試作開発に至ればと願っております。
なお検品後の製品であっても作動不良は起こりうるので、そのような場合の保障を肩代わりし製造者の負担を軽減する、互助制度のような仕組みが関連地区自治体にできればと思います。
巨大地震はプレートの境界付近で起こります。
地球内部のマントル対流により、その表面を構成する複数のプレートがそれぞれの方向へ一定の速度で移動しながら互いにぶつかり合い沈み込むときに、より強固なプレート接触箇所の摩擦で境界付近のプレートに圧縮や折り曲げ変形が起こり地震のエネルギーが蓄えられます。
接触箇所がスリップして摩擦で蓄えられていたエネルギーを解放する時、それが地震発生の瞬間であり、間隔の違いは多少あれど空白期間を経た後、確実に再発します。
その様子をSeismic Monitor/IRIS Eduにより視覚的に捉えることができます。
日本列島付近の地震の様子は、IRIS Earthquake Browser-Japan Regionの○印にマウスポインター合わせてより詳しく知ることができます。
お住まいの地区に関する詳細情報は地震調査研究推進本部の地震予測地図にて確認できます。
![]()
![]()